シャーベット救出班は、潮の引いた海沿いを、黙して進む。
途中までは、順調だった。
だが、ここはヨーグル島に近いだけあって、魔物の類が出没する。
一同、剣を抜いて魔物を倒しながら進む。
海賊達の話では、断崖絶壁のその下に、その小屋はあるらしい。
海賊達の中から、ウイスキーだけが同行している。
雨の中ただ、魔物を切り裂いて進んだ。
砂が足下に鈍くまとわりつく様に、歩みを阻んだ。
それでも進んでいた。
だが、ヨーグル島が近いという事は、それだけ魔物も強いという事だ。
量が、半端ではない。
「くっ・・・。」
剣士の中で腕が一番劣るのは、ガナッシュだった。
ガナッシュが剣を始めたのは、事実的には子供の頃だが、
実際まともな剣術が身に付いたのは、歌劇の一座を抜けてからだ。
一番、道が浅かった。周りは、幼い頃から修行を積んでいた者ばかりだ。
時々ガナッシュは、自分の剣を「にわか剣術」と言ってアールグレイに怒られることがある。
一人で身を立てるため、彼女は剣をとった。
しばらく傭兵家業で稼いでいた。
傭兵で稼げるほどの腕にまでなるのに、1年かかった。
それでも驚くべき早さで我流剣術を身につけた。
それも、アールグレイに出会って、自信が崩れ落ちた。
彼の剣の腕は、自分とは雲泥の差がある。
でも。
ガナッシュには、もうひとつ、シチュードバーグ騎士団に名を轟かせる、武器がある。
魔法だ。
ガナッシュが魔道に填ったのは、小さい頃に暇つぶしに読んでいた魔道書に始まる。
これが、面白い。
もともと剣士を志していた少女だったが、才能は魔法の方にあったらしい。
一番初歩的な炎魔法を、ただ一度で使いこなした。
次に覚えたのは、「アリナ・ルシール」。初歩の回復魔法だった。
小さな頃から、精霊の姿を見ることが出来た。
騎士団ではなく、魔道士の道に、よく誘われるガナッシュだ。
「量が半端じゃないな・・・。」
魔物のむれに嫌気が差してきたガナッシュが呟いた。
「何十匹いるんだよっ!!!」
そう叫びながら、アールグレイは確実に一人で半数を片付けた。
「すげえな、アイツぁ。」
ウイスキーが感嘆する。
「でやぁっ!」
プディングが、持ち前の速さをもって、それに続いた。
だが、砂に足を取られて、若干鈍ってはいた。それでも驚くべき速さだった。
プディングの武器は、その速さだ。
打撃だけでは、もともとの細腕と小柄さで、力ないところがあるが、速さだけは、騎士団一だ。
後衛には、カリーの王子が二人いた。
二人は、魔道剣士だ。魔力を帯びた剣を用いる。
カフェラーテは、どちらかというと剣士タイプだった。普通の剣士としても修行を重ねている。
だが、魔道への道へ彼を誘うは、婚約者と、兄だ。
「お前は横道へ逸れたよ。」
昔兄に言われた言葉だった。
剣士としては、カリー騎士団の隊長格にも登る。
だが、幼い頃から、この兄を見てきた。
ラズベリーは、剣士としても一流な上、魔道に大層長けた。
弟にしてみれば、兄は憧れの存在だった。
10歳でライト・セージになった。
その前に、たった4歳でリル・セージ(一番下の魔道士の総称)になったのだ。
こんな王子は、カリーの歴史にはいなかった。
最も、アプリコットなどは、生まれてから一番最初に発した「言葉」が
「アーグ・レーダ」
・・・光魔法の初歩の呪文だったという逸話があるが。
そんな者達が側にいたのだ。カフェラーテ一人、剣に打ち込むのは、
何だか仲間はずれに感じたくらいだ。
「横道に逸れた」とは言わせないと、カフェラーテは負けない位修行を積んだ。
やればやるほど、自分は剣士向きなのだと感じるが、
魔道の面白さもなかなか、一度填ると抜け出せない、まさしく魔の魅力があるのだと知った。
「アールグレイ、ちょっとどけていてくれ。」
ガナッシュはそう言うと、左手を前にかざした。
「あ、わかった。」
アールグレイは魔物を蹴散らしながらも、ガナッシュが魔法を放つだけの空間を空けた。
「よし・・・。ウェルダ・ヴィアーダ・エルフローデ!」
そう唱えた瞬間、炎と風が、嵐の様に渦巻いて、魔物達を切り刻んだ。
「よっしゃ!流石!」
嬉しそうなアールグレイ。
「貴女は、魔道士になった方がよろしいのではないですか?
いやはや・・・素晴らしい。属性二つを同時に操るのは、せめてミドル・セージクラスに
ならないと出来ないものですけれどね。」
ロゼがそう、解説めいた言葉で、絶賛する。
気付いたら、目の前に道が出来ていた。
「流石だな、ガナッシュは・・・。僕には二属性同時をあんなに簡単には、できな・・・」
カフェラーテは、感嘆の言葉の途中で、突然意識を失った。
「カフェラーテ様!?」
プレッツエルが倒れる彼を受け止めた。
「・・・大丈夫だ・・・。」
カフェラーテではない声が、した。
立ち上がったカフェラーテの表情が、違う。
「俺が出ようとすると、決まって気を失うんだ、カフェラーテは。」
カフェラーテの口は、カフェラーテの声ではない声でしゃべる。
「そういえばそうだったな。」
そう言ったのはラズベリーだった。
「・・・誰ですか、貴方は。」
そう聞くのは、ロゼ。
「俺か。そんなに驚かなくてもいいだろう。俺はビネガー。そう言えば、解るだろう。」
カフェラーテの姿をした精霊神は、そう名乗った。
「精霊神ビネガー・・・!?」
驚いた声でそう言ったはガナッシュだ。
「ええと・・・?カフェ様が、ビネガーって、ことか?」
と、アールグレイ。目を見開いている。
「そういう事だ。ほら、急いでる筈だな。手伝ってやろうと思って出てきた。
もうすぐ雨もやむ。急ぐぞ。細かいことは後で話してやる。」
そう言いながら、カフェラーテ、いや、精霊神ビネガーは、剣を構えつつ歩き出す。
ビネガーは、精霊神一の剣使いだった。
主に剣術の神として崇められる。
そんなビネガーにも弱みがある。ライバルのソルトだ。
熱血漢のビネガーは、クールなソルトによくからかわれていた。
剣にも魔道にも通じるソルトに、幾度となく挑み続けては負けていたという、人間達の知らぬ内情がある。
ソルトが付いていながら・・・。俺が居ながら・・・。
あっさりと、ミーソにしてやられた。
ミーソとビネガーは、仲があまり良くなかった。
どんなに声をかけても、どんなに気を配ろうと、ミーソはいつも拒絶した。
ミーソに一番心を砕いていたのは、ビネガーかも知れない。
いつも、ミーソは何でも壊した。
そう、ビネガーは思っている節があった。
一番平和を愛したビネガーだった。精霊神5人がまとまりの悪いことをいつも嘆いていた。
奔放なシュガー。
気にはなるが苦手なソルト。
天の邪鬼でまるで子供のソイソース。
根暗でひねくれ者のミーソ。
これをどうにかまとめたくて、頑張っていたのがビネガーであった。
何処か、カフェラーテに似ていた。
それが、正にカフェラーテの内に居た・・・。
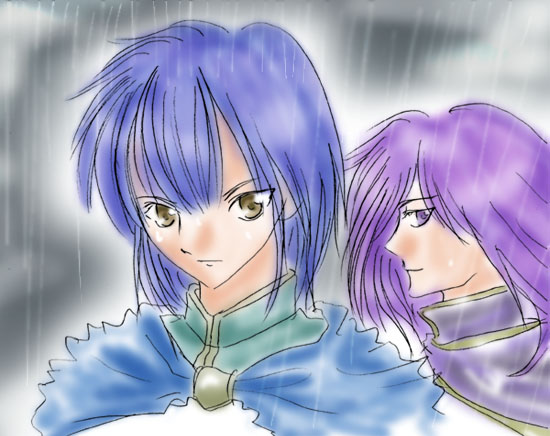
「そうだ、アールグレイ、ガナッシュ。剣を変えろ。その首にかけている剣にな。」
振り向いて、ビネガーはそう言った。
「え?あ、ああ、そういや忘れてた。パエリアちゃんに貰ったやつのことだよな?」
そう言いながら、アールグレイは首にてをやった。
「そうだ。その剣は、退魔の剣ガルダーヴァという。そして、ガナッシュが持っているのが聖剣カティナスという。魔物には特効があるぞ。それを使え。」
ビネガーが言う。
「この剣が・・・聖剣・・・?そんなものだったのか・・・?
・・・・・パエリアの奴、何処で手に入れたのか聞いておけば良かったな・・・。」
ガナッシュは、首のペンダントを手にとって、剣を抜いた。
「いい剣だろう。アールグレイもガルダーヴァを抜け。それからプディング。」
ビネガーは、プディングの前に立つと、プディングの首のペンダントを見る。
「な、なんだよ・・・。」
「この剣は、ヴァルクス・レイという。俗に勇者の剣と言われている様だが。
封印が解かれていないな。封印の鍵の呪文は知っているのか?」
「・・・?なんのことだ?」
「聞かされていないか?コークの一族でなければ、とけない封印だ。
俺の言う言葉を、剣に力を込めながら繰り返すといい。」
ビネガーは、一息置いて、再び口を開く。
「我が名において命ず。ヴァルクス・レイよ、目覚め我の力となれ。」
「わがなにおいて・・・命ず・・?ヴァルクス・レイよ・・・
我の・・・ちからとなれ・・・。」
プディングがそう、なんとか間違いなく唱え終えると、ペンダントは一本の剣へと
その姿を変えた。
「わっ、す、すげえ・・・。今まで何やってもなんともならなかったってのに・・・。」
プディングは興奮気味に剣を握る。
「懐かしいな。それは俺がコークにやったものだ。さあ、急ぐぞ。」
カフェラーテの姿をした戦神は、くるりと向きを変えて歩き出した。
「・・・・・何か、偉そうなカフェ様だなー・・・。」
そう呟いたのはアールグレイだった。
つづく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
はい、戦力強化しております。
今回は簡単ながら挿絵も入れてみました。青い髪してるのは、カフェラーテです。
後ろにいるのは兄貴。
続きます。
続き
もどる